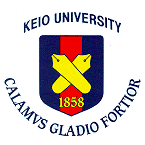卒業できるレポートのノウハウをすべて無料メルマガにて授けます
歴史(西洋史)のレポート
歴史系科目のレポートの進め方は、「史実の説明→考察を加える」となります。レポートの一般的な流れは、「テキスト理解→考察」なので、テキスト理解の部分を歴史の知識に当てはめた形となります。
歴史系科目の「考察」には、特徴があります。史実に考察を加えるとは、歴史的事実を説明して、その事実から何が言えるかをまとめるということです。
このページでは、「歴史(西洋史)」のレポートをお見せしながら、説明と考察の書き方について解説します。
著作権の関係上、レポート課題は掲載できませんが、テーマとしては「アメリカ革命の経過と歴史的意義について」となります。そのため、レポートに記述すべき項目は、次の2点になります。
ちなみに、これらは上述の史実と考察に該当します。
キーワードを書き出す
大まかな流れを決めた後、細かいステップを決めます。
その際、「節」という概念が必要になります。レポートは「説明」と「考察」という2つの要素があるので、それに応じて「説明節」と「考察節」に分けられます。節の作り方はこちらのページをご覧ください。
節立ての際気を付けることは、説明節の数です。説明すべき項目ごとに節を作るので、予めキーワードを用意します。
今回は以下のようになります。
キーワードを明確にすることで、過不足なく説明できるようになるので、必ず行うようにしてください。
このように言うのも、説明型レポートで失敗する原因は、説明不足が圧倒的多数を占めるからです。
例えば、アメリカ革命の説明の箇所はよく書けているのに、憲法の説明を適当に済ましてしまう人がいます。このような説明不足があると、それ以外の箇所が完璧でも再提出となってしまうので、説明の際は十分気を付けてください。
キーワードを明確にした後、節立てを行います。このとき、上記キーワードと対応させることがポイントです。
その結果、次のように節立てできます。
説明のポイント
それでは、実際のレポートをお見せするので、「説明」の書き方を学んでいきましょう。
上述したように、レポートには「説明→考察」という2つの要素があります。説明は考察の材料なので、事実の特徴について色濃く打ち出しておくことが重要です。
今回は第3節に注目して、考察に繋げられる説明の書き方を解説します。
第3節:合衆国大統領成立までの歩み
アメリカ合衆国は独立したものの、13の独立州の連合体にすぎず、中央政府である連合議会の権限が弱かったこともあり、政治的・経済的困難が続いた。そこで、強力な中央政府を樹立する気運が高まり、1787年にフィラデルフィアの憲法制定会議で合衆国憲法が作られた。
まずは背景を説明し、少しずつ掘り下げます。
憲法制定までには、いくつもの困難が待ち受けていた。合衆国憲法を支持する連邦派と、これに批判的な反連邦派が対立した。連邦派と反連邦派には、イギリスのような中央集権支持者と、それに反対する州権擁護者などが混在しており、広く意見を出し合った。また、農業を中心とする北部の対立や、大きな群と小さな邦との対立なども絡むなど、様々な対立が見られた。しかし、アメリカ合衆国は、これらの対立を乗り越えるのに十分な妥協の精神を持ち合わせており、会議の雰囲気は終始紳士的であり、道理をわきまえていたという。
背景について詳しく述べた後、合衆国憲法成立の過程について説明します。多くの説明項目を用意しておくと、その後の考察の助けになります。
この憲法は共和制民主主義を土台とし、中央政府の権限を従来より強化する連邦主義を採択した。また、行政権は大統領が率いる政府が行使し、立法権は各州から代表が集まる下院が行使し、司法権は最高裁判所が行使することも決めた。これにより、互いに抑制しあい、権力が一つに集中することを避ける三権分立の原則を定めた。
このように多角的に述べることで、合衆国憲法の意義、ひいてはアメリカ革命の歴史的意義が浮かび上がります。
考察の書き方
続いて、第四節をお見せしながら、「考察」の書き方について解説します。考察については、こちらのページをご覧になってください。
第四節:アメリカ革命の歴史的意義
アメリカ革命の時点では、植民地は本国に対して隷属関係にあり、それを覆すことは経済的・政治的事情によりほとんど不可能と考えられていた。そのような状況の中、独立を成功させたこの革命の意義は、世界の独立運動の啓示となった点にあると思われる。また、憲法において世界初の導入である「成文憲法」、「三権分立」などを制定した点についても、後の民主政治に与えた影響は大きいと言える。
考察とは、事実から何が言えるかを予想することです。歴史科目の場合、史実を積み上げた結果、浮かび上がってきた事実を分析します。例えば、「後に与えた影響」を述べることで、史実が持つ意味を位置付けます。
このとき気を付けることは、主観を述べただけでは考察と認められないことです。レポートは感想文ではないので、完全な主観を書いてはいけません。例えば、「この革命を学習して、~が印象的であった。」などと書いてしまうと、評価はかなり下がります。
そうではなく、「~と思われる」という言葉を用いて、客観性を示しましょう。「~と思う」は完全な主観ですが、「~と思われる」は「だれでも自然とそう思える(状況である)」という意味があります。
したがって、「根拠+~と思われる」と締めくくることで、客観性を保持できます。今後、あなたのレポートにも取り入れてください。
このようなレポートに関する講義は、メルマガにて詳しく解説しています。全100通の講義をすべて無料で受けられるので、こちらから登録して、学びを加速させてください。
関連ページ
- 「論理学」レポートで学ぶ、正しい説明順序の組み立て方
- 実際の「論理学」のレポートをお見せして、正しい説明順序について解説します。
- 「文学」レポートで学ぶ、文学系科目における本論の展開
- 実際の「歴史(文学)」のレポートをお見せして、文学系科目の本論の展開の仕方について解説します。
- 「生物学(第3回・完)」レポートで学ぶ、テーマと問いの設定
- 実際の「生物学(第3回・完)」のレポートをお見せして、レポートのテーマと問いの設定の仕方について解説します。
- 「社会学史Ⅱ」レポートで学ぶ、文献要約の仕方
- 実際の「社会学史Ⅱ」のレポートをお見せして、文献要約の仕方について解説します。
- 「社会心理学」レポートで学ぶ、レポート課題に最適な具体例の探し方
- 実際の「社会心理学」のレポートをお見せして、レポート課題に最適な具体例の探し方について解説します。
- 「教育学」レポートで学ぶ、テキスト批評の仕方
- 実際の「教育学」のレポートをお見せして、テキスト批評の仕方について解説します。
- 「教育心理学」レポートで学ぶ、考察を加えるポイント
- 実際の「教育心理学」のレポートをお見せして、考察を加えるポイントについて解説します。
- 「倫理学」レポートで学ぶ、専門用語の理解の仕方
- 実際の「倫理学」のレポートをお見せして、専門用語の理解の仕方について解説します。
- 「国語学」レポートで学ぶ、文学鑑賞の仕方
- 実際の「国語学」のレポートをお見せして、文学鑑賞の仕方について解説します。
- 「英語学概論」レポートで学ぶ、具体例の使い方
- 実際の「英語学概論」のレポートをお見せして、文学鑑賞の仕方について解説します。
- 「英語音声学」レポートで学ぶ、項目別の説明の仕方
- 実際の「英語音声学」のレポートをお見せして、項目別説明の仕方について解説します。