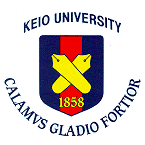卒業できるレポートのノウハウをすべて無料メルマガにて授けます
知識を次に活かす
どの科目から勉強すれば良いか分からないとき、手当たり次第に始める人がいます。これは、わざわざ向かい風を選んで走るのと同じです。
陸上では向かい風より追い風の方が良いタイムを出せますが、慶應通信で科目を選ぶ際にも同じことが言えます。
慶應通信のような長期スパンの勉強では、できるだけ効率的に勉強を進める必要があります。
これはある科目の知識と経験を、他の科目にも活かすことで可能になります。
このようにして、単位を重ねる度に効率性が上がり、科目選択においてより良い選択を取れるようになるのです。
基礎から応用に向けて学ぶ
勉強の鉄則は、基礎から学ぶことです。基礎から学べば、一切の無駄がないからです。
例えば、「社会学」→「社会学史Ⅰ」→「社会学史Ⅱ」の順序で学べば、社会学が何を扱う学問か、誰のどのような理論があるかなどが分かります。
そのため、「社会学のどのような点に関心があるか」が明確になった状態で、「社会学史Ⅰ」や「社会学史Ⅱ」に取り組むことができます。
また、「社会学」の勉強は、「社会心理学」の準備になります。そこから「教育心理学」へ、さらに「教育学」へ移行するなど、自動的に次のレポートが決まります。
このようにして、「何を勉強すれば良いか分からない」という状態から脱することができるのです。
まずは総合教育科目を履修し、その後専門科目に移行することが、履修計画の鉄則となります。
関連科目を履修する
慶應通信の科目には多くの関連科目があります。この点を考慮した履修計画を組むことで、より効率的に勉強を進めることができます。
例えば、「心理学」の関連科目には、「社会心理学」、「教育心理学」、「心理学Ⅰ」、「心理学Ⅱ」などがあります。スクーリングも含めると、その数は膨大です。
また、「社会心理学」は「心理学」と「社会学」の関連科目で、「教育心理学」は「教育学」の関連科目です。
関連科目は同じ理論が用いられるので、初めて学ぶ場合に比べ、様々な点で不可を減らして進めることができます。
そのため、最初に一通りの分野の科目を履修したら、その後は新規開拓より、既存の知識を活かすことを考えましょう。
関連科目については、「テキスト科目履修要綱」に詳しく掲載されているので、今後の履修科目のヒントとして活用してください。
関連ページ
- 入学から卒業までの履修計画の考え方
- 慶應通信の入学から卒業までの履修計画の考え方を説明したページです。
- テキスト単位取得の流れ
- 慶應通信のテキスト単位取得の流れについて説明したページです。
- スクーリング単位取得の流れ
- 慶應通信のスクーリング単位取得の流れについて説明したページです。
- レポート科目を決める3つのポイント
- 慶應通信のレポート科目を決める3つのポイントを説明したページです。
- お勧めの3分野科目
- 慶應通信のお勧めの3分野科目について説明したページです。
- 持ち込み可の科目を選ぶ理由
- 慶應通信の科目試験で持ち込み可の科目を履修する重要性について説明したページです。
- 科目試験の難易度を考慮する重要性
- 慶應通信の科目試験の難易度を考慮する重要性について説明したページです。
- 得意分野を構築する履修計画のポイント
- 慶應通信で得意分野を構築する履修計画のポイントについて説明したページです。
- 科目選択のセオリー
- 慶應通信の科目選択のセオリーについて説明したページです。
- 3ヶ月以上先まで計画を立てると失敗する理由
- 慶應通信では3ヶ月以上先まで計画を立てると失敗する理由について説明したページです。
- 科目選択のチェックポイント:「群」という概念
- 慶應通信の科目選択のチェックポイントを教えます。