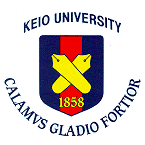卒業できるレポートのノウハウをすべて無料メルマガにて授けます
論理的な文章展開
よく勘違いしている人がいますが、レポートは正しいことを書けば合格できるというものではありません。テキストや文献通りの内容を書いているのに不合格となることは多々あります。
つまり、正しい文章と合格できる文章は、完全にイコールではないのです。
そのため、あなたは正しい文章ではなく、合格できる文章を書かないといけません。
このページでは、合格できる文章の特徴について解説します。
まず、合格できる文章には論理的な文章展開が見られます。
これは一文一文が矛盾なく繋がっていて、読み手にとって分かりやすく展開された文章です。
例えば、「AならばB」「BならばC」という前提を述べた上で「AならばC」と結論すれば、誰でも理解できるので論理的な展開です。
ただ、ここでもし「BならばC」を記述しないとどうでしょうか。
「AならばB」から「AならばC」を直接結論すると文相互の結びつきが不明瞭になり、読み手は疑問を抱きます。こういった展開は論理的と言えません。
このように記号だと簡単に理解できますが、実際の文章になると判断が難しくなります。
よくある失敗例として、定義づけしていない言葉を用いて説明したり、因果関係が不明瞭なまま結論を出してしまうことが挙げられます。
こういった問題は、各節が文章全体に対してどのような役割を果たしているかを把握することで解決できます。
文章の根拠を示す
合格できる文章のもう一つの特徴は、客観的な文章だと言えます。
簡単に言えば、根拠がある文章です。
どんなに論理的で分かりやすい文章でも、それが正しい内容かは別問題です。客観性とはこの「正しさ」に関する問題なので、自分の述べた内容が正しい事実であることを示す必要があるのです。
その方法は簡単です。
参考文献から根拠となる文章を引用すれば良いのです。
引用には、あなたの文章に説得力をコーティングする効果があります。先行研究を引用すれば、正しい事実であることを示すことができ、あなたの主張は誰にも否定されなくなるからです。
そのため、レポートで主張を述べる際は、その根拠を参考文献から引用しましょう。
記述方法としては、以下の通りです。
〇「〜引用文〜」と述べられている。(『文献名』、p.〇〇より引用)
〇「〜引用文〜」と述べられている。※注 (脚注:『文献名』、ページ数より引用)
引用の目的
このように効果的な引用をすることで、あなたの文章に説得力が生まれます。
実際のところ、多くの人は引用の目的をはき違えており、不要な引用を行っています。
引用は「根拠を示す」手段なので、用語や理論の定義づけや具体的な数値に対して行いましょう。
また、引用文の直後に自分自身の解釈を示すなどして、テキストのコピペにならないように注意してください。
このように正しく引用することで、読み手に自分の述べた内容が正しい事実であることを示すことができます。その結果、客観性が保持されます。
このようなわけで、合格できる文章は単に正しい文章ではありません。
正しい内容であることはもちろん、読み手にとって分かりやすい展開で、きちんと根拠が挙げられている文章のことを言います。
こういったポイントを抑えているかどうかで同じ内容でも評価は変わるので、「評価を得るにはどうすれば良いか」という視点も必要になります。
関連ページ
- 下書き完成後に見直す3つのポイント:内容、形式、表現の留意点
- 慶應通信のレポートの下書き完成後に見直す3つのポイントを教えます。
- レポート用紙の使い方に関する注意点
- 慶應通信のレポート用紙の使い方に関する注意点を教えます。
- レポートの文章が持つ性質:公共性がある文章の特徴
- 慶應通信のレポートの文章が持つ性質である、文章の公共性について説明します。
- レポートの文章が持つ性質:客観性がある文章の特徴
- 慶應通信のレポートの文章が持つ性質である、文章の客観性について説明します。
- レポートの重大な忘れ物:論述における問いと答えの重要性
- 慶應通信の論述における問いと答えの重要性を教えます。
- 慶應通信にはびこるコピペ問題:コピペを引用に変える方法
- 慶應通信のレポートでコピペを引用に変える方法を教えます。
- 「要」点を「約」す:重要な文章だけを短くまとめる「要約」
- 慶應通信のレポートの要約について説明します。
- 慶應通信のレポート不合格者必見:分かりづらい文章の3つの特徴
- 慶應通信のレポートにおける分かりづらい文章の3つの特徴を教えます。
- レポートの文章パターン:テキスト理解を示す「説明」という文章
- 慶應通信のレポートにおける「説明」という文章を教えます。
- レポートの文章パターン:「考察」についての大まかなイメージ
- 慶應通信のレポートにおける考察とはどのような文章かを説明します。
- レポートの文章が持つ性質のまとめ:公共性、客観性、考察の視点
- 慶應通信のレポートが持つ性質をまとめました。