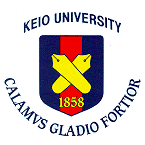卒業できるレポートのノウハウをすべて無料メルマガにて授けます
「説明」の趣旨
レポートの文章の1つに「説明」があります。
文章作成の際まず考えるべきことは、その文章の要件や趣旨です。要は「何のための文章か」です。
例えば、要約は「要点を短くまとめること」です。そのため、論理的に完璧であることより、「短さ」や「簡潔さ」が重視されます。
それでは、「説明」はどうでしょうか?
レポートは「テキスト理解→考察」という流れで進め、「根拠がある者同士の対話」を行います。これは、テキスト理解を示した上で、自分の主張を述べるという議論を意味します。
「テキスト理解→考察」のうち前半が説明に該当するので、テキスト内容を文字通り「説明」します。
このように言うと、要約と似ている気がしますが、両者は少し異なります。
要約は要点だけを記載し、「詳しくは本文を読んでください」という誘導の役割を持ちます。
それに対して「説明」は、テキスト内容を一通り述べます。
要点はもちろん、派生項目まで丁寧に説明し、論理的に組み立てる必要があります。
こうした文章がなぜレポートに必要かと言うと、「私はテキスト内容を理解しています」というアピールのためです。説明できるというのは、その確たる証拠となるからです。
以上が説明の趣旨です。
テキストを再構成する
ここまで読めば分かりますが、説明と要約との違いは、単にテキストから文章を拾うだけではNGで、構成も含めて自分で考えるということです。
この意味で、説明とは「テキストを再構成すること」と言えます。
再構成のコツは、テキスト内容を「分類する」ことです。テキストには同種のものが別々に記載されていたり、無関係のことが一緒くたに記載されることは多々あります。
そこで、これらを整理して必要なものだけを分かりやすく書き直します。
再構成には、文献から引用も有効です。引用によってあなたの説明が本当に正しいことが示され、文章に客観性が付与されるからです。
引用後には、その内容を分かりやすく解説するとなお良いです。解説と言うと難しく聞こえますが、文献の言葉を分かりやすい日本語に直すというイメージです。
このような作業を行えば、あっという間にテキストの「説明」ができあがります。
説明型レポートの評価は、書き手がテキスト内容を理解しているかの1点で決まり、読み手がそれを判断するには書き手の「説明」を読むしかありません。
自分の言葉で説明できるのは、それが100%である証拠です。
関連ページ
- 下書き完成後に見直す3つのポイント:内容、形式、表現の留意点
- 慶應通信のレポートの下書き完成後に見直す3つのポイントを教えます。
- レポート用紙の使い方に関する注意点
- 慶應通信のレポート用紙の使い方に関する注意点を教えます。
- レポートの文章が持つ性質:公共性がある文章の特徴
- 慶應通信のレポートの文章が持つ性質である、文章の公共性について説明します。
- レポートの文章が持つ性質:客観性がある文章の特徴
- 慶應通信のレポートの文章が持つ性質である、文章の客観性について説明します。
- レポートの重大な忘れ物:論述における問いと答えの重要性
- 慶應通信の論述における問いと答えの重要性を教えます。
- 慶應通信にはびこるコピペ問題:コピペを引用に変える方法
- 慶應通信のレポートでコピペを引用に変える方法を教えます。
- 「要」点を「約」す:重要な文章だけを短くまとめる「要約」
- 慶應通信のレポートの要約について説明します。
- 慶應通信のレポート不合格者必見:分かりづらい文章の3つの特徴
- 慶應通信のレポートにおける分かりづらい文章の3つの特徴を教えます。
- レポートの文章パターン:「考察」についての大まかなイメージ
- 慶應通信のレポートにおける考察とはどのような文章かを説明します。
- レポートの文章が持つ性質のまとめ:公共性、客観性、考察の視点
- 慶應通信のレポートが持つ性質をまとめました。
- 評価を得るにはどうしたら良いか:正しい文章と合格する文章は違う
- 慶應通信のレポートにおける正しい文章と合格する文章の違いを教えます。