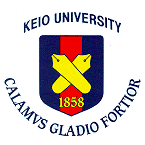卒業できるレポートのノウハウをすべて無料メルマガにて授けます
大学教育の目的は「学問」すること
大学教育の目的は「学問」です。
学問とは字の如く、「学び、問う」勉強スタイルです。「学び、習う」だけの「学習」とは違い、「自ら問いを発し、答えを出す」ことが大学教育の神髄と言えます。
したがって、この「学び、問う」という要素を、レポートに取り入れる必要があります。
この考え方ができているとレポートは一気に上達し、慶應通信のすべてはうまくいきます。
ただ、レポート課題によっては、「学び、問う」のに困ってしまう場合もあります。
例えば、「〜について説明せよ。」という課題があるとします。
このような課題では、あるテーマについて一通り説明することが要件なので、「答え」自体がありません。そのため、問いを立てる必要がなく、テキスト内容を「学び、習う」ことに終始します。
一方、「〜について自由に論じなさい。」という課題はどうでしょうか。
このような課題では、自分で問いを設定し、それに対する「答え」が必須です。テキスト内容を「学び」、そこから論点を定めるために「問う」必要があります。
前者を説明型レポート、後者を論述型レポートと呼びます。
このように慶應通信のレポートには2種類ありますが、学問としてのレポートは論述型レポートになります。
論述とはレポート上の議論である
このようなわけで、慶應通信における勉強とは「学問」であり、それはレポートで論述することだと言えます。
そこで、論述について大まかなイメージを掴んでもらいます。
論述とは、レポート用紙上で「議論」を行うことです。
議論には議題があり、論点があり、議決があります。論点は論じる価値があり、結論は皆を納得させるだけの説得力が必要です。
したがって、論述は「問いを発し、議論を経て、結論に至る」という順序で進めます。そのため、レポートに以下の要素が必須となります。
・問いと答え
・テキスト理解→考察
・双方向のコミュニケーション
問いと答えは、論述の最も基本的な要素です。問いがないと論点が定まらず、そもそも学問でなくなります。
学問には「学び、問う」という2つの過程があるので、これに対応して論述も2段階で展開します。
それが「テキスト理解→考察」という論述の流れです。論述ではテキスト内容を自分の言葉で説明し、その内容を踏まえて考察を行います。
最後に、主張形成の方法です。議論は根拠がある者同士の対話によって進めるため、論述には双方向のコミュニケーションがないといけません。
テキストのコピペや根拠がない感想は、コミュニケーションの方向性が一方通行なので、仮に内容が正しくても合格することができないのです。
このように大学教育の目的を1つ1つ意識してレポートを書くことで、慶應通信のすべてはうまくいきます。
関連ページ
- レポートを書く時の気持ち:レポートで議論する
- レポートを理解するには、議論の仕方を勉強するのが一番です。このページでは、レポートと議論の類似点を教えます。
- レポートを通じた科学的態度とは?:レポートにおける引用の意義
- 慶應通信のレポートにおける引用の意義を教えます。
- レポート分析のテクニック:レポートの文章を区切る重要性
- 慶應通信のレポートにおける文章を区切る重要性を教えます。
- レポート初学者が陥りがちな罠:テキストや文献読解に対する考え方
- 慶應通信のレポートにおけるテキストや文献読解に対する基本的な考え方を教えます。
- 対話とおしゃべりの違い:レポートは根拠がある者同士の対話である
- 慶應通信のレポートは根拠のある者同士の対話です。
- レポートと作文の違い:コミュニケーションの方向性
- 慶應通信におけるレポートのコミュニケーションの方向性を教えます。
- 慶應通信の常識はずれな真実:レポート課題に対する認識を正す
- 慶應通信のレポート課題に対する正しい認識を教えます。
- レポートの中の仮想の話相手:レポートにおける主張形成の仕方
- 慶應通信のレポートにおける主張形成の仕方を教えます。
- 「節立て」についての大まかなイメージ
- 慶應通信のレポートにおける「節立て」についての大まかなイメージを教えます。