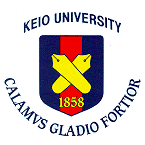卒業できるレポートのノウハウをすべて無料メルマガにて授けます
正しい参考文献の探し方
客観的で説得力あるレポートを書くには、文献を参考にしたり、引用することが基本となります。
ただ、なかには文献活用について理解が浅く、そもそも何を読んだら良いか分からないという人がいます。
このページでは、文献に対する考え方について広く説明します。
まず、文献なら何でも参考文献になるかと言うと、そうではありません。
基本的には、学術書以外NGです。参考文献は「学問としての文献」が対象なので、書店に並んでいるビジネス書や市立図書館にある資料集などは、参考文献として認められません。
インターネット閲覧に関しては、論文のPDFなどきちんと出典を明記できる場合のみ、参考文献として認められます。
このように言っても、似通った文献が多いので自信を持って選択できないという人が多くいます。そこで、最も確実な方法を教えます。
慶應義塾大学のメディアセンターで探すことです。
当たり前ですが、メディアセンターの文献はすべて参考文献の条件を備えています。そのため、あれこれ悩む前にメディアセンターへ行き、その中から探せば良いのです。
このとき、真っ先に探す文献は決まっています。
『テキスト科目履修要綱』の「参考文献」欄で指定されている文献です。
これらの文献には、レポートに書いてほしい内容が詰まっています。それなしにはレポート課題の要件が読み取れない場合がありますし、一切読んでいないというのは印象が良くありません。
このようなわけで、指定文献は1冊でも良いので参考にして、文献表に記載することが大切なのです。
文献表への記載
続いて、文献表への記載について説明します。
文献表には参考文献と引用文献があります。
参考文献は、レポート作成にあたり参考にした文献のリストです。
少しでも読んだ文献は参考文献になるので、レポート本文に引用していない場合もきちんと記載する必要があります。
注意点として、レポートに無関係の文献やページは記載する必要がありません。例えば、50ページ〜100ページまで読み、そのうち70ページ〜100ページまでレポートに関係する場合、参考文献としては70ページ〜100ページとなります。
引用文献は、レポート本文で引用した文献のリストです。
引用を行った場合、参考文献とは別に文献表を作成します。本文に注を付して脚注に出典を明記し、参考文献と区別しましょう。
例外として、テキストは参考文献ではありませんが、引用した場合は引用文献となります。
文献活用の目的
ここまで読めば、文献活用に対するイメージも固まってきたと思います。
最後に、なぜ学術書以外はレポートの文献として認められないかについて解説します。
レポートは自分の考えを自由に述べる場ではなく、科学的根拠を持った者同士の「議論の場」です。参考文献や引用文献は、この議論において客観性を高めるという役割を持ちます。
議論では主張の際、それを形成する「情報源」が重要な役割を果たします。
この適切な「仕入れ」を行うのが、参考文献です。文献表に明記するのはそのためで、どこの誰か分からない情報を拠り所にして、レポートを書いてはいけないということです。
また、自分の主張は他人の意見と区別する必要があります。文献内容をコピペして自分の主張のように展開するのを避けるため、引用文には注を付すのです。
このように文献活用には目的があるので、気をつけて選択するようにしてください。
私の場合、最初にテキストにあたり、次に指定文献にあたりました。その後、補足としてキーワード検索を行い、必要な情報を集めました。
3〜5冊ほど文献を揃えたら十分にレポートを書くことができるので、指定文献の他、読みやすい文献を中心に手元に揃えてください。
関連ページ
- どこまで掘り下げれば合格できる?:文献読解と文章作成の相互作用
- 慶應通信のレポートにおける文献読解と文章作成の相互作用を教えます。
- テキストや文献が難しく感じる理由:テキスト理解のマインドセット
- 慶應通信のレポートにおけるテキスト理解のマインドセットを教えます。
- レポート課題に対する思い違い:レポート課題を正しく理解する方法
- 慶應通信のレポート課題を正しく理解する方法を教えます。
- 真っ先に探すべき参考文献とは?:参考文献の探し方と選び方
- 慶應通信のレポートの参考文献の選び方、使い方について説明します。
- レポートの難易度を下げる:レポート課題からテーマ設定する方法
- 慶應通信のレポート課題からテーマ設定する方法を教えます。
- 他人の文章は分からない:意味不明な参考文献にあたったときの対処法
- 慶應通信で意味不明な参考文献にあたったときの対処法を教えます。
- レポートの合否と文字数の関係:レポートの文字数に関する問題
- 慶應通信で合格するレポートの書き方を教えます。
- 「文献の探し方」を学ぶ:参考文献を探す2つのテクニック
- 慶應通信のレポートの参考文献を探す2つのテクニックを教えます。