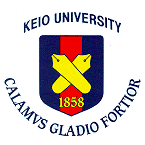卒業できるレポートのノウハウをすべて無料メルマガにて授けます
バランスの良いレポートの特徴
レポートは「序論、本論、結論」の形式で文章を展開します。それぞれの箇所では、必要な内容を過不足なく述べる必要があります。
このページでは、「序論、本論、結論」の分量と役割について詳しく説明します。
まずは、レポート全体からみた分量の目安を教えます。
・序論 全体の5%以内
・本論 全体の80%以上
・結論 全体の15%以内
この割合で文章を区切ることで、バランスの良いレポートを作成できます。
例えば、全体を4000文字でまとめる場合、序論100文字、本論3500文字、結論400文字程度で作成すると良いでしょう。慶應通信では1単位につき2000文字が原則なので、2単位科目のレポートを書く際は参考にしてください。
さて、文字数の内訳としては、本論が大部分を占めていることが分かります。これは、本論が「テキスト理解」「考察」などの論述を行う箇所だからです。
一方、序論と結論は数文で完結し、それほど多くの分量にはなりません。本論の要約を行う分、結論の方が分量が多くなります。
序論の目的
序論の目的とは、レポート全体の方向性を示すことです。何について、どのような問いを設定し、どのような方法で述べるかを宣言します。
そこで、次の3点を明記します。
・テーマ
・問い
・本論の予告
まず、レポート課題からテーマを設定します。
テーマ設定には、レポートで述べる範囲を限定するという意図があります。限られた文字数で際限なく述べることはできないためです。
テーマは「〜について」の形で明記しましょう。
続いて、問いを設置します。
勘違いしている人がいますが、テーマだけではレポートは書けません。テーマの中の具体的な論点が定まっていないからです。
論点がない状態で書き始めると、必ずと言って良いほど内容が拡散し、何が言いたいのか分からないレポートになってしまいます。
そこで、レポートで解決すべき問いを設置します。問いは具体的な論点となり、これに答えを出すことでテーマについて論じることができるのです。
問いは、「〜なのだろうか?」という疑問文の形で明記しましょう。
最後に、本論の予告を行います。
これから本論を読む人に向けておおまかなレポート構成を周知し、テーマや問いに対するアプローチを述べます。
本論の予告は、「第1節では〜について、第2節では〜について述べる。」など、節のタイトルを列挙する程度で十分です。
以上3点を守ることで、序論はレポート全体の方向性を示すことができます。
本論の目的
本論の目的とは、論述を行うことです。序論で決めたテーマ、問いについて論述し、解決へ導きます。
本論はレポートの中核をなし、レポートの合否に直接関係します。絶対に欠かせない内容は、次の2点です。
・テキスト理解
・テキスト内容を踏まえた考察
本論の流れは、「テキスト理解→考察」です。
テキスト理解とはテキスト内容を自分の言葉で説明し、考察の準備をすることです。また、考察とはテキスト内容を踏まえ、問いに対する答えを出すことです。
その際、様々な内容を一緒くたに扱うことはできないため、説明項目や文章の役割に応じて区切る必要があります。
そこで、「節」を作ります。節は結論のスモールステップとして機能し、本論はいくつもの節から構成されます。
節立ての際は、「第1節:タイトル」のように表記し、3節程度作ると良いでしょう。
例えば、「テキスト理解(1節、2節)→考察(3節)」という構成にすることで、節を進めるごとに、序論の問いに対する答えに迫ることができます。
結論の目的
結論の目的とは、レポート全体を振り返り、レポートを終了することです。
結論と言うと、「学んだ意義」や「今後の意気込み」を書いてしまう人がいますが、こうした感想を述べる箇所ではありません。
結論では、序論の問いに答えを出し、文字通りレポートの結論を導きます。
そこで、次の3点を明記します。
・テーマと問い
・本論の要約
・問いに対する答え
まず、テーマと問いを挙げましょう。
「本レポートでは、〜について述べるため、…という問いを立てて考察した。」というように、当レポートにおける問題意識がどのように始まったかについて、読み手と再度確認します。
続いて、論述の歩みを確認するため、本論の要約を行います。
「本論では第1節で〜、第2節で〜を述べた。」というように、節ごとの要点を簡単に述べる程度で十分です。
最後に、序論の問いに対する「答え」を明記しましょう。
この点が結論で最も重要です。本論で導いた答えを、必ず結論にも明記してください。
関連ページ
- 構成が分かりやすいレポートの特徴:章と節の基礎知識
- レポートの章や節の基礎知識を説明します。
- 調べた内容がすべて重要に思える人へ:レポート構成をイメージする節立て
- 節立てによるレポートのイメージ付けについて教えます。
- レポートによる議論の実例:「序論、本論、結論」が論述に果たす役割
- 論述を可能にする「序論、本論、結論」の形式を教えます。
- 論理的な文章の裏側にあるもの:レポートにおける述べる順序の重要性
- 慶應通信のレポートにおける述べる順序の重要性を教えます。
- レポートの難易度を決める問い:レポートの根幹にある2つの形式
- 慶應通信のレポートの形式で守るべき2つのルールを教えます。
- テーマと問いは何が違うのか?:レポートにおける必要性と関係性
- 慶應通信のレポートにおけるテーマと問いの違いを教えます。