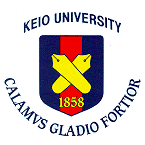卒業できるレポートのノウハウをすべて無料メルマガにて授けます
レポートの形式を丸暗記で済ましてはいけない理由
レポートの形式のうち最も有名なものは、「序論、本論、結論」の形式です。ただ、それぞれの役割についてはあまり知られていません。
レポートを書く上で重要な考え方は、この形式を守るのではなく、使いこなすことです。そのためには、どこで何を書くかを丸暗記するのではなく、なぜそうなるかを理解することが大切です。
このページでは、論述型レポートの形式の学び方について解説します。
レポートの目的は、「学び、問う」という学問です。そのため、レポートには問いが必須となり、最初に示す必要があります。
そこで、序論に問いを設置します。
また、レポートの文章には、「議論」「公共性」「客観性」などの性質があります。
議論の際、「議題」や「進行次第」はいち早く告知され、共有される必要があります。これらは、レポートではそれぞれ「テーマ」「本論の予告」に対応します。
そこで、序論では「テーマ」や「本論の予告」も明記し、レポートの方向性を示す必要があります。
このようにレポートの形式は、レポートの目的や性質と密接に関連しています。
レポートの形式の学び方
これらの準備が整い次第、本論に移行します。
レポートの文章には、公共性と客観性という性質があります。つまり、分かりやすく説得力がある文章でないといけません。
これは、文章を内容ごとに区切り、論理的な構成を意識することで可能になります。
そこで、「節」を用意します。
説明項目や考察へ移り変わる際に節を立て、文章を区切ることで、それぞれの内容を深く記述することができます。また、全体の構成も整理できるので、論理的な欠陥を見つけやすくなります。
このように節を活用し、本論における議論を進めましょう。
さて、議論には究極的な目的があります。それは、「議決」を出すことです。
レポートでも同じで、問いに対する答えは必須です。
そこで、結論に答えを明記します。
よく「結論で何を書けば良いか分からない」と言う人がいますが、そういう人は序論に問題があります。
序論に問いがないから、答えが出ないのです。そのため、序論と結論をきちんと対応させて、答えを明記してください。
また、議論を終了するにあたり、要点を振り返ることも大切です。
そこで、結論では序論のテーマと問いを再度述べ、本論を要約しましょう。
このようにレポートの形式は、レポートの目的や性質と関連付けて理解することで、初めて使いこなすことができます。今後は単なる丸暗記で済ますのではなく、形式の学び方について理解してください。
レポートの形式については、こちらのページから学んでください。
関連ページ
- 自ら問いを立てて論じ、答えを出す:論述型レポートの要件
- 慶應通信の論述型レポートの要件を教えます。
- 節は結論へのスモールステップ:論述型レポートにおける節立て
- 慶應通信の論述型レポートにおける節立てについて説明します。
- 「範囲」に対して「切り口」を決める:論述型レポートのテーマ設定
- 慶應通信の論述型レポートのテーマ設定を教えます。
- 卒業の扉を開くカギ:論述型レポートを定義する「問い」
- 慶應通信の論述型レポートを定義する「問い」について説明します。
- 文献を題材とした科学的予想:論述型レポートにおける考察の加え方
- 慶應通信の論述型レポートにおける考察の加え方を教えます。